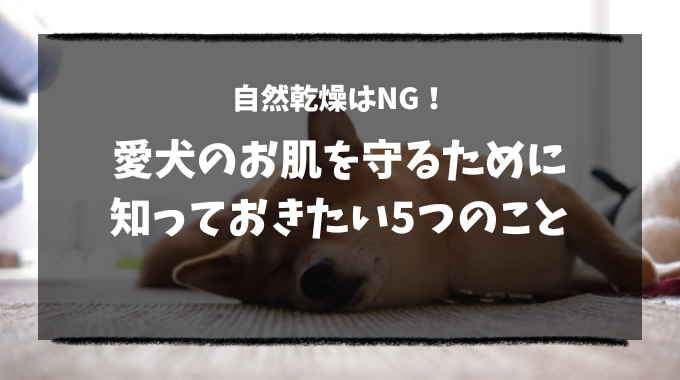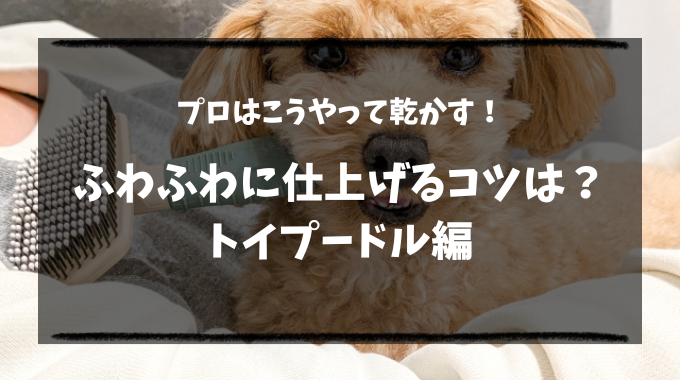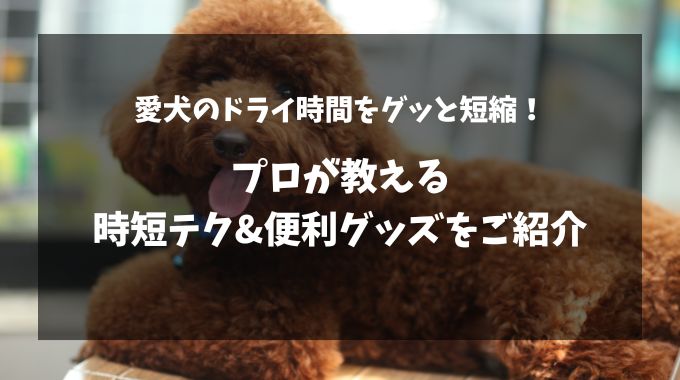シャンプー後の「犬の乾かし」は、健康を守るうえでとても大切なステップです。
しかし、「うちの犬は乾かすのが苦手だから」「自然乾燥で十分」と思って、つい乾かさないままにしていませんか?
実は、犬を乾かさないとどうなるかを知らずに放置すると、皮膚炎やカビ、被毛のもつれなど、思わぬトラブルにつながることがあります。
この記事では、犬を乾かさないとどうなるのかというリスクから、乾かすときのコツ、道具選びまで詳しく解説します。
愛犬の健康と快適さを守るために、ぜひ最後まで読んでみてください。
苦手意識のある犬にも優しくケアできる方法を知れば、毎日のケアがもっとスムーズに、そして愛犬との絆も深まります。
- 自然乾燥のリスクがわかる!
- 犬を乾かす必要性が知れる!
- ドライヤーが苦手な子のアドバイスがわかる!
- トリマー歴10年
- トリマーの専門学校卒業
- 地元のトリミングサロンで10年以上勤務
- これまでに1,000頭以上のわんちゃんと関わる
- 社団法人ジャパンケネルクラブ C級トリマーライセンス(2015年2月取得)
- 一級愛玩動物飼養管理士(2015年2月取得)

犬を乾かさないとどうなるかリスクを5つ紹介

犬を自然乾燥させてしまうと、皮膚トラブルや体温の低下、においの発生など、健康面での問題が多く起こります。
ここでは、その代表的な5つのリスクを詳しく紹介します。
- 皮膚病や湿疹の原因になる
- 雑菌・カビの温床になりやすい
- 被毛のべたつきや悪臭の原因になる
- 体温が低下や体調を崩すこともある
- ノミやダニが繁殖しやすくなる
皮膚病や湿疹の原因になる
濡れた状態が長く続くと、犬の皮膚はふやけてバリア機能が低下し、細菌や真菌が繁殖しやすくなります。
これにより、赤み・かゆみ・フケなどの皮膚炎や湿疹の原因になります。
特にシャンプー後は毛穴が開いており、刺激に敏感な状態なので注意が必要です。
皮膚トラブルは繰り返すと慢性化しやすく、日々のケアで予防することが大切です。
雑菌・カビの温床になりやすい
濡れた被毛は雑菌やカビが繁殖しやすい環境です。
これらは、皮膚から嫌なにおいがする原因にもなります。
特に通気性の悪い部屋や梅雨時期は要注意です。
しっかり乾かすことで、においや病気を防ぐ効果が期待できます。
被毛のべたつきの原因になる
自然乾燥させると、皮脂や水分が被毛に残り、べたついてしまいます。
べたつくと、毛が絡まりやすくなり、毛玉の原因に。
犬は毛玉をほどく際に、痛みを感じてしまうこともあります。
愛犬の清潔感を保つためにも、濡れたまま放置するのは避け、きちんと乾かしてあげましょう。
体温が低下や体調を崩すこともある
特に小型犬や子犬、高齢犬は、濡れたままでいると体温が急激に下がりやすく、風邪のような症状を引き起こすことがあります。
夏場でもエアコンの風などで体が冷えることがあるため注意が必要です。
タオルでしっかり水分を取ったあと、ドライヤーでやさしく乾かしてあげることが重要です。
ノミやダニが繁殖しやすくなる
湿った毛のまま放置すると、ノミやダニが好む環境を作ってしまいます。
皮膚をかゆがる、かさぶたができる、などのサインが出ていれば要注意です。
また黒い小さい粒のようなものが体にあれば、ノミの糞かもしれません。
完全に乾かすことで寄生虫の発生リスクを下げ、快適で衛生的な環境を保つことができます。
犬を乾かさないのは絶対NG!乾かす必要性とその理由

濡れたままの状態は犬の健康に悪影響を及ぼします。
乾かすことは皮膚・被毛を守る基本ケアであり、愛犬との信頼関係を深める大切な時間でもあります。
自然乾燥がNGな犬種の特徴
自然乾燥では不衛生になりやすく、特にダブルコートや長毛種は蒸れやすいため注意が必要です。
たとえばゴールデンレトリバーやポメラニアン、シーズー、プードルなどは、毛の密度が高く通気性が悪いため、乾きにくく皮膚トラブルを起こしやすくなります。
乾き残しによる湿疹やカビの原因にもなるため、自然乾燥ではなく、タオルやドライヤーを使った丁寧な乾燥が必須です。
犬種に合わせたケアを心がけましょう。
皮膚や被毛の健康を守るケアの基本
乾かすことは皮膚を清潔に保ち、健康な被毛を育てる基本のステップです。
特に梅雨時期や冬場は湿気がこもりやすいため、しっかり乾かすことでトラブルを予防できます。
さらに、乾かす過程で抜け毛や異常を早期に発見できるメリットも。
日々の健康チェックとしても大切なケア時間です。
飼い主との信頼関係にも影響する?
ドライの時間は、飼い主が犬に触れ、声をかけながら過ごす貴重なコミュニケーションの場です。
優しく丁寧に乾かすことで、犬は安心感を覚え、飼い主との信頼関係が深まります。
逆に、雑に扱ったり無理に進めたりすると恐怖心を与えてしまい、今後のお手入れが苦手になることも。
ゆっくりなれさせていくことが大切ですね。
ブラッシングやドライヤーを嫌がる子も、日常的に楽しくケアしてもらえることで徐々に慣れていきます。
ドライヤーが苦手な犬の乾かし方のコツ3つ

ドライヤーを怖がる犬にも安心して乾かせる方法を紹介します。
音や風に敏感な子への対処法や便利グッズを活用し、嫌がられずにケアするコツを解説します。
音や風を怖がらせない環境づくり
犬がドライヤーを怖がる原因の多くは「音」と「風の強さ」です。
テレビや人の話し声をBGMにすることで、ドライヤーの音を目立たせず、犬がリラックスしやすくなります。
風の当て方にも注意が必要で、いきなり顔に風を当てると恐怖心を抱かせる原因になります。
後ろ足やお尻など、刺激の少ない場所からゆっくり当て始めるとスムーズです。
また、短時間で切り上げるようにして、嫌な印象を与えない工夫も大切です。
ペット用静音ドライヤーやグッズの活用
最近ではペット専用の静音ドライヤーや、ハンズフリードライヤー、ドライボックスなど便利なアイテムが豊富に登場しています。
とくに静音ドライヤーは、音が小さく風の強さも調整可能で、怖がりな犬でも受け入れやすい設計になっています。
また、両手が使えるスタンド型のドライヤーなら、片手で犬をなでながら乾かすことができ、安心感を与えることができます。
グルーミング用のドライルーム(ドライボックス)も、一定の温風を送りながら安全に乾かせます。
愛犬の性格に合わせて道具を選ぶことで、ストレスのないケアが実現できます。
タオルドライの工夫で時短乾燥に
タオルドライをしっかり行うことで、ドライヤーの時間を大幅に短縮できます。
まず吸水性の高いマイクロファイバータオルを使いましょう。
水分を軽く押し当てるようにして吸い取るのがポイントです。
こするように拭くと、被毛が痛んだり皮膚を刺激したりするためNGです。
小型犬なら、タオルを体に巻いて包み込みながら吸水すると効果的。
数分おきにタオルを替えれば、かなりの水分を除去できます。
また、タオルを数枚用意して交互に使うことで、短時間で効率的に水分を取り除けます。
タオルドライのひと工夫が、ドライヤーへの負担を減らし、犬のストレス軽減にもつながりますね。
犬を乾かさないことで起きた実際のトラブル事例

「自然乾燥でも大丈夫」と思っていると後悔することに。
犬を乾かさなかったことで実際に起きた皮膚トラブルや動物病院での症例を具体的に紹介します。
動物病院でよく見かける症例とは?
動物病院では、「乾かさなかったこと」が原因と考えられる皮膚疾患をよく見かけます。
代表的なものは「湿性皮膚炎(ホットスポット)」で、濡れたままの状態が続くと皮膚がふやけ、細菌が繁殖しやすくなります。
また、耳の中が湿ったままだと「外耳炎」や「マラセチア性皮膚炎」のリスクも高まります。
特に垂れ耳の犬種や毛が密な犬種は通気性が悪く、症状が悪化しやすいため注意が必要です。
獣医師に「きちんと乾かす習慣を」と指導されるケースも多く、正しい乾かし方が健康管理に直結することがわかります。
放置が原因で悪化したケース
たとえば以下のような事例があります。
雨の日の散歩後にそのまま放置していたら、翌日から皮膚に赤みやかゆみが出てきた
シャンプー後に自然乾燥させていたら、体をやたらに掻くようになり、病院で皮膚炎と診断された
このように、乾かさなかったことで皮膚炎などが悪化したケースは少なくありません。
「面倒だから」と後回しにした結果、愛犬がつらい思いをすることのないよう、飼い主として正しいケアの意識を持つことが大切です。
まとめ:犬を乾かさないとどうなる?病気を防ぐための3つのポイントとは?

今回は、「犬を乾かさないとどうなるのか」ご紹介しました。
最後に、「犬を乾かさないとどうなる?」という疑問に対して覚えておきたい3つの大事なポイントを整理しておきます。
- 自然乾燥のリスク
- 正しい乾かし方
- 犬に合わせたケア方法
この3つをおさえておけば、愛犬の健康管理はぐっとラクになります。
自然乾燥のリスクをしっかり把握して、適切なケアをしてあげたいですね。